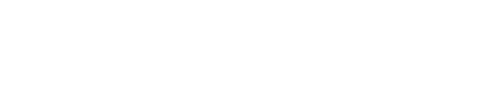■ロイクのルーとティー■
二番目の高校に行くようになってから、少しだけ進路の事を考えるようになった。絵の世界も捨てきれないし、音楽業界も少し気になる。
どちらにせよ、高校の進路指導では納得のいく答えは無さそうだったので、とりあえず好きな事を好きなだけやろうと思った。
今迄とは違うエリアで遊ぶようになった僕は、福生のライブハウスやプールバーで遊び狂っていた。福生には横田基地があり、どこの店に行っても必ずと言っていいほど外人が居た。
今はどうだか知らないけど、当時福生のバーでは$が使えた。
カウンターで$紙幣を出してビールを飲んでいる外人達はえらくカッコ良く見えた。外人達にくっついて歩いている日本人の派手めの女性もたくさん居た。そのうちの一人と少しだけ話すようになった。
17才の夏の暑い日の事だった。
その女性と話をしていたら年齢は24才の帰国子女で、住んでいる場所はウチから割と近いマンションに一人暮らしなので、帰りは車(赤いサーファー仕様のファミリア)で送ってくれるという。「ラッキー!&大人の女!」と思った僕は眠くなるのを我慢して、何かを期待し、深い時間まで福生のバーで遊んでいた。
そろそろ帰るから車を取って来るというので店の外で待っていると、赤いファミリアが目の前にやってきた。ファミリアの座席にはTown&CountryのTシャツが着せてあった。
で、よく見ると彼女は運転をしていない。助手席に座っている。
運転席には「目と歯」しか見えない。
よく見ると黒人のおっさんがニタニタ笑いながら運転していた。
僕が後部座席に乗り込むと「I'm Lou ルーデス」と言いながら握手を求めてきた。とりあえず握手をしてニタニタ笑い返した。
送ってもらう車中で、そのルーとカタコトの日本語と英語で、通じてんだかどうなんだか分からない話を色々した。
なんでも普段はエアフォースのコンピューター技師をしていて、日本に来て1年半ぐらいだという。なんだかよく分からないけど仲良くなり、恐らくこの彼女と付き合っているみたいだし、彼女の事は忘れて、この黒人と友達になった。連絡先をもらい、この頃は携帯電話なんか無いので、基地の電話交換の番号と彼の部屋の内線番号みたいなのが書かれた紙だった。
僕の実家の電話番号も渡した。
はじめてこの番号に電話した時は、ものすごく緊張した。
だって交換の人は外人だし、英語が通じなくて他の部屋に繋がったらなんて言って謝ったらいいのか分からないし、繋がってもちゃんと会話出来るのかも自信がなかった。
でも何とかいいかげんな英語で話は通じ、また遊ぶ約束をした。
それからたまにルーと遊ぶようになり、他の仲間も紹介してもらったりして、僕は週末になると横田基地まで遊びに行き、ルーの家で触った事のないパソコンを使わせてもらったりした。
コモドール社のAMIGAという機種で、このパソコンでフライト・シミュレーターなんかをやらせてもらい、やたらと興奮した。
基地の中には当時日本にはなかったバーガーキングというハンバーガーショップがあった。
初めてなんとかワッパーというアホみたいな大きさのハンバーガーを食べた時は「俺は今、アメリカを食っている」。と本気で思った。
基地の中で音楽をやっている人達とも知り合いになり、僕も自分のベースを持ち込み、セッションをやらせてもらう機会があった。
この頃の僕は中央線沿線ではそこそこ腕のある高校生ベーシストとして有名になっており、演奏テクに関しては自信があった。
ふだんレコードのジャケットでしか見た事のない外人達に混ざって、果たして自分のプレイがどれほど通用するのかちょっとビビったけど、僕はその基地の中に居るどのベースプレイヤーよりも上手く、黒人ぽいプレイが出来た。
外人達は僕のプレイを見て、どうやって弾くのか俺にも教えてくれ!と盛り上がり、僕は有頂天というか天狗になった。
チョッパーベース(親指で弦をはじきながら弾く技法)は、ビデオも無い時代だったので、レコードを聞きながら、どうやってその音を出すの独自に考えたオリジナルの奏法だったので、ある黒人ベースプレイヤー(へたくそ)は高校生の僕に弟子入りをした。
あ、俺もしかしてプロになれんじゃね?と考え始めたのがこの頃だ。
そんなこんなで、基地のすぐ外にあった教会で日曜日にゴスペルをやるから、お前がベースを弾けと言われ、やらせてもらう事になった。
何十人かの黒人が、一斉に歌う。そんなのは見た事がない。
この時は緊張もしたけど、それより何より、その迫力に感動してしまった。
思えば貴重な体験だ。本当に楽しかった。
ずっとこの時間が続けば良いと思った。
半年ほどが過ぎて、ルーがアメリカに帰る事になった。
ルーと知り合うきっかけを作ってくれた女性は、ルーとはとっくに別れて他の黒人と付き合っていた。
彼女から別れ話をされた時、ルーは死ぬほど落ち込み、勢い余って彼女の住んでいたマンションの十階の部屋まで、外の配管をよじのぼってベランダから部屋に侵入して、警察に通報されたらしい。バカだ。
その初めて出来た外人の友達のルーが遠く離れたアメリカに帰るという出来事は、僕にはショッキングな出来事だった。
もう一人、僕がベースを教えていたティーという黒人が居た。
彼は奥さんも子供も居て、建設作業員として基地で働いていた。
彼は毎日いろんな建物を作って、基地の中のアメリカンサイズのアパートメントで、奥さんと二人の子供と一緒に幸せに暮らしていた。
基地の中にはあらゆる職種があって、マーケットで働いている人も居れば、電気屋さんも居るし、ボーリング場とかもあって、そこで働く人も居る。小さいアメリカがそのまんまそこに在るという感じ。道路も街並みも日本のそれとは全く違って、まるで映画のセットみたいに見えた。
たった3~4メートルの高さの有刺鉄線の向こうなのに違う国。
なんだか不思議だった。
ティーの家族とは本当に仲良くしてもらった。週末は一緒に基地内のマーケットに行って買い物をして、信じられないほど巨大な肉塊や、業務用洗剤みたいな大きさのコーラを買って来て、アパートのベランダでBBQをしたり、連休があると軍用機に乗せてもらい沖縄の嘉手納基地までバケーションに連れて行ってもらったりした。
ティーはルーとは違って真面目というか、大人しい男だった。
見た目はNBAの選手みたいにデカくて、身長も2メートル位あった。
外で遊んでいるとき彼は、いつも日焼けを気にしていたのだが、僕にはどこが日焼けしてんのかも分からないし、「俺、日焼けしてない?」って聞かれても何と答えていいのか分からなかった。
あれはジョークだったのか、それとも本気だったのか、今でもよく分からない。
彼に紹介してもらった、基地の外にいる外国人の友達も何人か居た。
一人は色男の黒人で、日本語も堪能。僕が「何年ぐらい日本に住んでるの?」と聞いたら、流暢な日本語で「まる十年」という返事が返ってきてビックリした。
もう一人は調子のいい性格の黒人で、エディという男。
エディは分倍河原のアパートで、一人暮らしをしていた。
このエディとはこの後、ずいぶんと長い付き合いをした。
エディは昼間はどこかの会社でコンピューター関係の仕事をして、夜はDJ FAST EDDIEという名前でクラブのDJをやっていた。
よくエディの家に泊まりに行って一緒に音楽を作ったりした。
彼の家にはタイプライターみたいな形をしたアップルⅡがあって、僕はこの時にアップルのパソコンを初めて触った。クリーム色っぽいパソコンと6色リンゴのマークがカッコ良かった。
エディの家でレコードを聴いたり、楽器をいじったりしてるうちに朝になって、それでも元気なエディは狭いキッチンに立ち、パッケージに黒人のおばさんが描かれているパンケーキミックスを水で溶いて適当に焼いたのと、カリカリに焼いたベーコンで朝メシを作ってくれたりした。
そのパンケーキミックスがメチャクチャ美味かったので、今でも紀伊国屋とかナショナルマーケットに行くと探しているけど、まだ見つからない。
思い出の味だ。